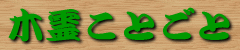 |
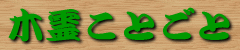 |
・・・・・・木霊ことごと(平成13年12月)・・・・・・![]()
柊(ひいらぎ)の葉のまろくなる姿こそ(61)
| ビワの花が人目を避けるようにして咲いている。茶の花も咲いている。アブがおしりを振りながら花 に頭を突っこんでいる。 柊の花も咲き残っている。みな、めだたない花だが香りはいい。ビワの花の香りはやわらかな甘さをも ち、茶の花には渋みのある甘さがある。柊の花はついこの頃までは立ち止まるほど、濃い香りを放ってい たが今はない。 柊の葉には独特の刺があって、これを鬼の目突きという。節分の日、魔よけ、鬼よけのために柊の枝を イワシの頭とともに門口に立てる習わしがかなり古くからあった。おもしろいのは、柊が五十年から八十 年ほど生長すると、葉のぎざぎざが自然に消えることだ。年輪を刻んで、次第に刺がなくなる。角がとれ てまるくなる。柊に学びたいと思うが、人間はなかなかこうはいかない。 葉に刺がある若木をオニヒイラギ、年をへて刺がなくなった老木をヒメヒイラギと呼ぷのも面白い。 冬空を背にして、あらかた葉を落した樫が、厳しい姿で立っている。宙に描かれたこずえの線は、繊細で しかも力強く、野放図のようでいて、ある調和を保っている。 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成13年11月)・・・・・・![]()
第60回 紫の花は人を鼓舞し、恩愛にみちている
| 秋も深まり冬に入るとアルプスの山々は白い衣におおわれはじめた。里ではリンドウの花が咲き、心に刺きささるような、青みがかかった濃い紫の色である。 夏目漱石が「虞美人草」の中で「燦たる一点の妖星」と表現した女の着物の色は、このような鋭い紫の色だったろうか。野口武彦のリンドウ賛歌には「満月粛条たる枯野に滴る紫の鐘状花冠のしずくは、まさしくこれ秋の唯一の色どりではないか」という一節がある。リンドウの色の濃さ、鋭さには、人の心を騒がせるものがある。 秋が深まるにつれてなぜか紫の花がめだってくる。場所によって、紫の花はアキノキリンソウの黄の花や、シロヨメナの白い花と一塊になって咲いている。身を寄せ合って咲くさまは、霜枯れの季節を前に、いとおしいものたちが最後のうたげの杯をかわしあっているようだ。 限りなく人間らしいもの、父らしいものなどなど、犯しがたく、また恩愛にみちたものが~今日、私たちを呼んでおり、鼓舞しているようである。 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成13年10月)・・・・・・![]()
第59回 紅葉季の木の実にはいのちがある
| 秋も深まってくると信州の山々もぐんぐん変ってくる。北アルプスには冠雪がはじまり、紅葉・黄葉はもう山川の川べりにまでおりてきている。 川の流れは光の角度で透明にもなり、淡い青緑色にもなる。白い河床にはるいるいと横たわって土に化しつつある枯れ木がある。ケシヨウ柳やオノエ柳の群落が川風にゆれている。 空に刺すカツラの黄葉はきはだ色とでもいうのだろうか。黄に染まる大樹のまばゆいばかりの明るさ岬、の中には、心に陰を落すものがある。ふり仰ぐと青空にしみる絹雲があり、逆光をあびた山々の針葉樹は不機嫌そうな陰をつくっていて、黄や紅の部分だけが浮き立っている。 山野の草木が美しい紅葉になるには条件がある。 ①晴天が続くこと、②その割合には温度が上がらないこと、③土壌中に燐酸の少ないこと、④土壌中に銅の存在すること、と矢野佑さんが「植物漫筆」の中で書いている。 やがて姿を消す葉の一枚一枚とは逆に、木の実の一粒一粒には、やがて姿を現すもののいのちがある。 「妻の手に木の実のいのちあたたまる」秋元不死男 |
・・・・・・木霊ことごと(平成13年9月)・・・・・・![]()
第58回 遠慮深げな声は沈吟にも通じよう
| ふるさとの土の底から鉦たたき 種田山頭火 深夜、カネタタキを聞くのは楽しい。チン・チンあるいはチツ.チツともきこえてくる。このチン・チツの数は、ひい・ふう・みい・よ、と数えて十を超えるときもあれば、七つ八つで途切れることもある。間をおいて、また間をおいて鳴きはじめる。この間合いのとり方が心にくいほどいい。カネタタキは闇の中にあって静寂を演出している。 命を燃やして鳴くアオマツムシの大合唱が、時によってうっとうしくなる。コオロギは已れの美声に酔う、といったところがある。それらに比べるとカネタタキの鳴き声はいかにも遠慮深げで、かぽそい。この虫は低木や植込みの葉陰に遠慮深げにすんでいる。 わが心ひそかに聞ゆ鉦叩 中村汀女 沈吟という言葉があるが、静かにくちずさむ、あるいは思いにふける、といった意味であろうか。カネタタキの鳴き声を聞いていると、心の内側によどむため息や、つぷやき声ととけあう。秋はひと日ごと天地の虫たちとともに、沈吟のときを迎えつつある。 |
・・・・・・木霊ことごと(平成13年8月)・・・・・・![]()
第57回 七夕星への祈りごころ
| 七夕は牽牛と織女、つまりひこ星とひめ星が年に一度出会いをする日だと伝えられている。しかしこの星合いは、実は旧暦七月七日の話で、現在は月遅れの八月七日に行う所が多い。 夏になると夕暮れと共に、二つの恋星が天頂に清明な光を放ち始める。空を仰ぐ。天の川にかかる白鳥座が羽をひろげている。その近くに白く輝くのが織女と牽牛だ。万葉の時代は、ひめ星のもとに急ぐひこ星の舟の音が聞こえてきたことだろう。 「七夕のちぎり」といえば、生涯変わらぬ男女の固い約束をさすが、近いようでも二っの星の距離は十五・五光年である。光りの速さは電波の速さと同じだから、もし織女が無線電話で「天の川の白鳥橋のほとりで待っているワ」とささやいても、その声が牽牛氏に届くまでは十五年半を要する。「きっとだぜ」という返事はそれから十五年かかる。星の恋は気長なものだ。 ところで近所の寺にクチナシの木があり、一つの花が散ると次の花が咲き立つの状態を続けている。七夕星とは異なるが、はるかなものへの祈り心が窺えるのであろう。 |
・・・・・・木霊ことごと(平成13年7月)・・・・・・![]()
第56回 風とともに流るるこころ
| 七月になると緑陰が恋しくなる。近くの公園を通ると、ベンチに日がさ姿の若い母親がすわっているのが見える。コブシやミズキのこずえが風にさざめきながらゆれている。近くには吹きわたる風に帽子を飛ばされながら子供たちが遊んでいる。 「風冴ゆる」の冬から、「風光る」の春へ、「風薫る」の青葉のころから「風涼し」の夏へ、日本人は風のたよりで季節を知り、風ということばにさまざまな思いをたくしてきた。風が季節の演出者だと感じとれるのである。 南の風にしても、春先に吹くのが春一番、花散らしくろはへで、五月の南風は薫風、青嵐、梅雨どきは黒南風、梅しろはへ雨明けのころは白南風と名づけられている。 風のたよりに耳を傾ける生活は、風雅とか風情とか風流とか、風の字のついたことばが結びつけられている。 日本人が風流ということはから受けとる感じは「心の中に涼しい風が吹いているような状態だ」といった人がいるが、当を得た解釈だと思う。大自然のなかにそっくりとけこまなければ、その本当の姿に触れることはできないけれど。 |