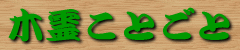 |
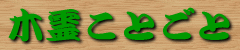 |
| 初夏の闇夜に、すいすいと光を放ちながら飛んでいる蛍は美しいばかりでなく、神秘的ですらある。「ほうほう、ほうたる来い、あっちの水は辛いぞ」という懐かしい唄は、誰でも記憶にあることであろう。 信濃では蛍の名所は、何といっても天竜川ほとりの辰野であろう。三、四回観に行ったことがあるが、蛍たちは「光のことば」で求め合う。雄は飛びながら明滅を繰り返す。雌は葉にとまって光りながら雄を誘う。その求愛の中に、人々は思いを残してさまよう霊魂を見、夜の妖魔の姿を見てきた。 田畑への農薬によって一時期、絶滅と思われた蛍も、各地の思い入れで小川にも蛍の火がとびかっている。 蛍は、成虫になってからはエサをとらず、水を飲むだけだ。幼虫時にたくわえたエネルギーで、頼りなげに飛びながら鋭い求愛の光を放っている。成虫の寿命は、雄が五日前後、雌が七日前後であるが、そのはかない命をひたすら恋に燃やしているのである。 死に急ぐなと蛍に水吹いて 鈴木真砂女 にんげんの手足ひらひら蛍沢 木内彰志 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成14年5月)・・・・・・![]()
いのちの鈴香秘めゆ (66)
| 鈴蘭には「きよらかな/雪のひかりを/花にして/かほりをすずしく/ひびかせる」ということばがあり、鈴蘭には北国の花らしい、清澄な香りがある。 日本には「君影草」の名があり欧州には「聖母の涙」の名がある。ドイツでは「五月の小さい鐘」と呼ぴ、その花のつき方から「天国への階段」とも呼ぷ。この花は人を詩人にするらしい。 五月一日に鈴蘭の花束を贈ると、贈られた人に幸福が訪れるといういい伝えがフランスにある。鈴蘭は愛の使者でもある。フランス語の「鈴蘭する」は「女に好かれようとする、女の前で気取る」意味と言っている人もある。 しかし鈴蘭が常にもてはやされるかというと、そうでもない。北海道では「ベコ(牛)も食べない始末の悪い草」といわれ、この草が群生する所は不毛の地だと嫌われている。詩と現実には落差がある。 近くの雑木林の片隅に毎年、鈴蘭が咲く。ほんのわずかな木漏れ日の中でりんりんと香りの鈴をならす花をみるたびに、「いのちの香り」がひびいてくる。 すずらんの鈴香秘めたる森ゆたか 道生 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成14年4月)・・・・・・![]()
土や樹木とともに風に化す呼吸を (65)
| 蕪村に「けふのみの春をあるいて仕舞けり」という句がある。桜の咲くころ、よく晴れて、気温が上がって、春の心が天地に満ちる日がある。春たけなわ、春の頂上は今日でおしまいだと思う名残日を「今日のみの春」と感じとったのであろうか。そんな日は、自然に足が動きだす。いつもながら近くの山里を歩き山桜を見た。 青い地衣をまとった山桜の古木の下でふりあおぐと、葉と花、えび色と白の点描の世界がこまかく風にふかれている。無数の虫が飛び交う花々の奥に、たそがれ前の露草色の空があった。 甘糟幸子さんは文庫本『野の食卓』の中で、山道を歩いたことに触れ、「私の足は……歩いていくうちに、大昔の人間はこんなふうに、土や樹木と一緒に呼吸したのかしら、山の中で木の葉の間を渡ってくる風にあたるのは楽しいものです。今では歩いている自分が風を起しているような気がする」と述べている。 大自然の山地の土と樹木のなかを歩きつつ、風に化すことのすばらしさを、しんみり味わいたい。 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成14年3月)・・・・・・![]()
人とともにある「こころあいの風」 (64)
| 春の風について辞典を拾ってみたら、春風、光風、和風、陽風、恵風など二十五種類もあった。そよそよ吹く風をさすことばは、軟風、微風、軽風、細風、なよ風など十五種類ほどあった。東風(こち)ということばでも、まごち、強ごち、風ごち、梅ごち、桜ごち、と多様な表現があり、風と日本人のつながりの深さがわかった。 二月下旬から三月上旬ごろ、海から吹いてくるやわらかな風を昔の人は「いなさ」といった。春一番、はなかぜ、青あらし、かりわたし、など風にはいい名前が多い。 北風が凍てついた街を吹き渡るさまは「風冴ゆる」で、そよかぜが常緑樹の葉をきらめけるさまが「風光る」である。「風青し」の初夏から「風死す」の盛夏をすぎて「風立つ」の季節へと、私たちの生活は常に風の便り、風の色と共にある。風雪、順風、風まかせ、と人生訓にも風がでてくるし、臆病風、役人風ということばもある。 このように風はその折々の竹林を鳴らし、熊笹を鳴らし、馬酔木の白い鈴を鳴らし、季節のこころを伝えている。季節のこころを伝えるああいう風のことを「こころあいの風」というのかもしれない。 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成14年2月)・・・・・・![]()
雪国びとの祈りごころ (63)
| 信州北信濃、越後は昔から雪国といわれてきた。降りしきる雪の中からキジバトの鳴き声が聞こえたり、スズメが一羽あるいは五、六羽連れだってきて、雪の上を跳びはねたり、裸木の雪をちらしたりしている景と出合うと、どこか心がなごむ。 いまはもう、雪見の風流を楽しむ人は少ないだろうが、雪見屋敷、雪見とうろう、雪見船、雪見酒などの言葉が日常に生きていたようである。山頂などの高台から見下ろすと、村の家々が綿でつくられたように見える。雪国の静かなたたずまいを感じ、そこに生き抜いている人達の姿、とくに雪に耐え忍びながらも、じっと生への祈りと、またそれに伴う人の人柄のまろさが育まれていく姿を目の当りにすることができるのである。 花を楽しむように雪を楽しむ、といったことは雪国では通用しないが、降る雪の中に草花の魂を見る、という心の働きは生き続けているようである。 降りつづく吹雪に耐えながら、それが同時に春の命を運んできてくれると信じることが、雪国に生を享けた者の心奥に語り継がれている。 |

![]()
戻る
・・・・・・木霊ことごと(平成14年1月)・・・・・・![]()
初春のことに生命力 (62)
| 初春の木々とくに裸木の美しさ、冬ざれの裸木からは全身全霊で自らの内にある春へのいのちをはぐくみ、かばい、守り抜こうとする気がまえが伝ってくる。 初春の花といえばシクラメンも挙げられる。白い炎、唐紅の炎、べにふじ色の炎、かがり火花とか、かがり火草とか呼ばれるこの花には常に炎の感じがある。 葉は密生していて、深い森を思わせる。その深い森の暗がりからすっくとくきが伸びて花をつける。花がくのつけ方が一風変わっていて、萼(がく)がうつむいているのに花びらは反り返って、上を向く。見事なほど、一斉に上を向く姿がかがり火にたとえられるのだろう。 葉をかきわけると、大小のつぽみが、噴きでる生命力を抑えるようにして出番を待っている。 「爪ほどの冬芽なれども天を指す登四郎」(13年作) 能村登四郎の一句がふと頭をかすめた。 |