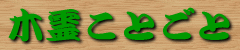 (平成19年12月) |
| 前ページに戻る |
| 天心に描かれた梢の裸姿こそ(133) |
| 湯本 道生 |
| 冬空を背にして、あらかた葉を落としたケヤキなどがきびしい姿で立っている。宙に描かれた梢の線は、繊細でしかも力強く、野放図のようでいて、ある調和を保っている。 「木霊」を発足して十一年。県下各地の会員ひとりひとりの詩情をこめた参加と努力によって、「木霊」独特と地味な道ひとすじのなかに、他の追随できない更なる境地を目途に、努力されてきたのである。 色変へぬ松にかこまれ魁夷館 小林久雄 わが翳の息あるさくら紅葉かな 倉科繁登 子規の忌のやたらめつたら栗落つる 笹井紀子 一日を心のまろく白露の日 保谷善蔵 天界へつづくかに組む父の稲架 米山聡子 などなど、その境地をよみがえらせるものがある。 目下担当している「㈹俳協県支部長」「県俳協顧問」「県『農業と生活』選者」「SBC『武田徹のつれづれ俳句」選者」などなど……天心に描かれたケヤキの裸婆の繊細さを、こころ深くとどめてゆきたい。 |
