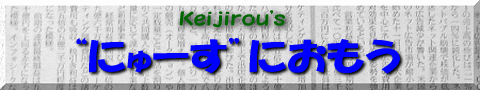社会            社会 社会            社会 社会 |
| バックナンバー(2001年1月〜6月)へ |
 教育基本法(011202) 教育基本法(011202)  |
先週、文部科学相の諮問により、中央教育審議会において教育基本法の見直しが始まった。現在の教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり、1947年に制定されたもので、50数年間改正はされてない。
今回の教育基本法見直しの視点は、「時代の変化に対応し、生涯学習や国際化、環境保全等を組み込む」「個人の能力や才能を伸ばし創造性をはぐくむ」「伝統・文化の尊重や日本人としての自覚を促す」「学校・家庭・地域社会の教育に対する役割を明確にする」「信教の自由や政教分離の原則に留意しながら宗教的な情操をはぐくむ」というものだ。
今まで、この教育基本法については、何回となく論議が交わされていた。改正論者は「基本法がうたう人間像には、日本人の民族的伝統や規範が欠落」しており、「教育目的に、忠誠や親孝行がない」こと等の問題を揚げていた。また、改正慎重論者は「戦前のような国家至上主義的・全体主義的な考え方に戻ってはならない」としていた。
私は教育基本法について熟知している訳ではないが、日本国憲法の精神にのっとった個人や個性の尊重等、その内容については普遍的なものが多く、50数年を経た現在でも大きな柱と成り得るものだと思う。むしろ問題なのは、教育基本法そのものではなく、現在の教育環境の変化に追いついていけない家庭・学校・地域社会のあり方ではないかと思う。
すなわち、現在起こっている学力低下・国際化教育の立ち遅れ、そして校内暴力・不登校・少年犯罪等の様々な問題に対して、この基本法の精神にのっとった教育や環境づくりがされてこなかったということだ。
「挨拶がきちんとできる」ことや「高齢者を敬う」ことなど毎日の生活の中での基本的な事柄や、相手を尊重し相手の気持ちを理解できるように育てることは「家庭でのしつけ」だ。また受験競争だけではない人間同士・他人同士とのふれあい・つきあいの重要性を理解させるのは「学校での教育」、そしてそれの重要性を子供自身が肌で実感でき、確認でき、納得することができる「地域社会の環境づくり」が必要なのだと思う。
具体的に、我々親はどうすれば良いのか、教師はどうあるべきか、そして地域社会人としてどうしていくべきかを考え、お互いにあるべき方向に向け真剣に継続して取り組んでいくしかないのではないか。法律やハードを変えても、人の心やソフトが変わらなければ、結局は何も変わらない。
上記三者の取り組みについて、言うことは容易だが、実行に移し継続させていくことはなかなか難しい。そして一朝一夕に変えられるものではないが、少しずつ少しずつ良い方向に変えていくしかないのだ。「国の政策が悪い」「学校や教師が悪い」と、現在の教育の問題を他に向けるのは、何の解決にもならない。一番重要なのは、「教育基本法」の問題ではなく、我々大人のひとりひとりの、このような自覚なのだと思う。
|
 狂牛病の安全宣言(011021) 狂牛病の安全宣言(011021)  |
9月10日、千葉県で狂牛病に感染した疑いのある牛1頭が発見され、英国の研究所での精密検査の結果、日本初の狂牛病感染が確認された。
その後、農水省の不明確な混乱した発表が火に油を注ぎ、スーパーの牛肉の売上げが激減、牛肉メニューを主力とする吉野家やマクドナルド等の外食産業にも大きな影響を及ぼし、全国の公立小中学校の36%にあたる1万1千校余りが給食で牛肉の使用を中止した。
政府は、感染源とみられている飼料用の肉骨粉の使用を禁止し、病原体が集まりやすい危険部位は健康牛のものも含めて全て焼却処分する等の安全対策をとった。また、脳やせき髄など危険部位を含む加工食品についても安全性の確認が行われた。そして先週の18日より、食肉処理場で解体され出荷される全ての牛に対して狂牛病感染の検査が義務付けられた。これらの対応により、政府は早い時期に「安全宣言」を出したいとしている。
今回の狂牛病問題は、ようやく終息の方向へ動き出したが、まだ多くの問題点が残されており、一般消費者の牛肉に対する不信感は全く拭われていない。
18日以降出荷された牛肉は安全性が確認されていたとしても、それ以前に出荷された牛肉や輸入牛肉の安全性確認はどうするのだろうか。農水省は、打撃を受けた畜産農家や飼料メーカー等の関係業者、売上高が激減したスーパーや外食店等の圧力に屈して安全宣言を尚早に出しているのではないだろうか。また、千葉県で確認された日本初の狂牛病感染牛は、問題の輸入肉骨粉を食べていないとのことであり、感染源についてもいまだ原因不明の状況になっているようだ。
現在の安全性の確認および今後の飼育・出荷・流通経路等における感染防止策や安全性維持の仕組みが、どうもまだ片手落ちのような気がしてならない。
また、全頭検査で狂牛病感染の疑いがあった場合の公表についても議論が分かれている。簡易検査の段階で公表は、国民に不安を与え、風評を助長する懸念があるため、政府の統一見解では、精密検査で結果が確認されるまで公表しない方針になっている。
しかし簡易検査時点で疑いのあるものは公表するという一部自治体もある。これは政府の統一見解に合わせるべきではないだろうか。かえって消費者に不信感を与えることになるだけだ。公表はしなくても、精密検査で結果が確認されるまで、疑いのある食肉の出荷をストップしておけばいいだけの話だ。
今回の狂牛病問題を含め、「O−157」「口蹄疫」「遺伝子組換え食品」等、食品の安全性についての最優先事項は、当然のことながら消費者に対する絶対的な安全性の確保および仕組化された安全性の維持だ。このこと自体は全ての人に異論はない筈であるが、これが建前として横に置き去られ、組織化された利害関係者寄りの政策も多く見受けられる。
我々は、直接目に見えて組織化されることが少ない一般消費者や国民の、利益や生命が損なわれることのないよう監視し続けることが必要だ。
|
 薬害エイズ・狂牛病・不祥事・・・(010930) 薬害エイズ・狂牛病・不祥事・・・(010930)  |
28日、薬害エイズ裁判で東京地裁は、業務上過失致死罪に問われた元厚生省担当課長に、非加熱製剤でHIVに感染・死亡させる危険の予見可能性が高くなっていた86年投与分に対して「危害の発生を未然に防止するための配慮を尽くす注意義務があった」として有罪判決を言い渡した。これは、「官僚の不作為」による刑事責任を認めた初めての司法判断となった。
薬害エイズ事件は、「官(厚生省)・業(製薬会社)・医(医師)」の癒着により、三者の複合汚染が安全対策を遅らせ、1400人以上が感染し、500人以上が死亡するなど多くの被害を出し現在もなお続いている。業(製薬会社)・医(医師)については既に一審の判決が下されている。
業(製薬会社)については、今年の2月に大阪地裁で、歴代3社長に「製薬会社は医薬品の安全性を確保する義務があるのに営業上の利益を優先し、危険性を軽視し非加熱製剤の販売中止や回収をしなかった」として有罪判決を下している。
医(医師)については、3月に東京地裁で「その当時の治療技術に照らすと、薬禍の発生・拡大を予測することはできない」として無罪の判決となった。そして今回、86年投与分に対して厚生省の担当課長に有罪の判決が下った。
今回の判決も含めて、司法の判決内容は評価できる。難しいのは、それぞれの立場において、どの時点で「感染や死亡の危険性を予知できたか」ということだ。その時期を裁判所が確定し、それぞれの状況での義務違反の有無について判決を下したことになる。
今再び問題となっているのは、薬害エイズ事件も含めて、官僚や公務員の体質や組織そしてモラルの問題だ。先日発生した狂牛病問題においても、農水省の対応について大きな批判がでている。国民の生命や健康を守る立場にある公務員が、権限を行使せず被害を発生・拡大させてきたことが少なくない。
また、今年の1月から連続して発覚した外務省官僚の一連の公私混同した、罪意識のない不祥事についても同様のことが言える。
官僚や公務員は、公僕として国民の税金により、国民の生命や安全を守り、平和で快適な生活を維持するためのスタッフである。反対に言えば、これらの公僕の義務不履行に対して、国民はもっと厳しく追及し怒らなければならない。公務員および国民の両者とも、その基本的なことが忘れがちになっている。我々国民はもっと賢くなる必要があり、国民のためにならない公務員はどんどん辞めさせるべきだ。
また、今回の元厚生省や農水省の対応の不適切さについては、比較的目に見え易いものだが、他の行政府や官庁についても同様のことが言える。米国多発テロに対する対応として、日本政府は、本当に国民のメリットになる判断をしているのだろうか? 日本の「国旗を見せる」ということは、自衛隊が出動することなのだろうか? 多くの疑問がある。
日本政府や行政・官庁の対応について、我々国民はもっと厳しくチェックし、監視していくことが重要だ。官僚や公務員はあくまでも国民の利益のためのスタッフであるのだから。
|
 「歴史教科書問題」再燃続(010722) 「歴史教科書問題」再燃続(010722)
|
扶桑社の「新しい歴史教科書」をめぐって、国内外で議論や抗議活動が再燃している。栃木県の一部の地域で、扶桑社の「新しい歴史教科書」が採択決定されたものの、一部団体の抗議等により再度検討を余儀なくされているという。また韓国の政治的圧力がますます強まり、韓国国民の採択反対集会や学生の日韓交流見直し等の事態も起こっているという。
日本の「教科書検定制度」は、中国や韓国の「教科書国定制度」と異なり、民間人の著述による検定合格教科書を各教育委員会や地域が選択できる制度を採用している。4月に検定合格した教科書の中から、今月(7月)より各市町村の教育委員会や地区が教科書の採択をする仕組みだ。特別な利害関係に影響されることなく、政治的な公平性が保てるものであるなら、中国や韓国の制度に比べて民主主義国家として優れている制度を採用していると言える。
各市町村の教育委員会や地区において、教科書の採択をめぐって多くの議論がなされ、最終的に一つに決まること自体は問題ない。ただその過程において偏った考え方による扇動や激しい非難中傷が繰り返されるということであれば問題だ。
6月の初めから扶桑社刊「新しい歴史教科書」の中学歴史・公民教科書が「市販本」として書店に並んでいる。また、その隣に賛成・反対派の本も合わせて販売されている。一般人にとっては容易に見ることのできない採択前の教科書の内容を知ることができるということは画期的なことだ。マスコミ報道だけに偏らず、直にその内容を見ることができるのだ。
我々の物の考え方は、新聞・テレビ・雑誌等のマスコミを通じた情報により無意識のうちに影響を受けてしまう傾向が大きい。今回の「歴史教科書問題」にしても「A新聞」と「S新聞」の論調は全く正反対だ。毎日の新聞紙面を単発的に見ているだけでは気づかないかもしれないが、両紙のホームページの「歴史教科書」特集を比べて見ると一目瞭然だ。「A新聞」の読者は知らず知らずのうちに「A新聞」の論調に洗脳されていってしまう可能性が高い。「歴史教科書問題」よりも「新聞報道問題」の方が問題なのかもしれない。
我々は偏ったマスコミ報道にとらわれることなく、多くの情報を幅広く入手できるよう心がけていきたい。その意味では情報発信を寡占化してきた従来型のマスコミに対して、インターネットの発達は、個人の幅広い情報収集力や個人の情報発信機会を高めてくれる。
最後に、「S新聞」の7月20日付け読者の声に「現行教科書はお粗末すぎる」と題して「従来の歴史教科書は、全国地図の基本図を作り上げた伊能忠敬や、東郷平八郎の記述はなく、韓国の英雄は登場している。これを偏向とは言わないのか」と掲載されていた。枝葉のことではあるが、私も全く同感だ。私は戦争肯定派でもなく、右翼的な考え方も持っていない。日本人の礼節や自信が失われつつあるのは戦後のこうした教科書や教育が一因のように思われるからだ。
|
 連続リンチ殺人事件判決(010715) 連続リンチ殺人事件判決(010715)
|
先週の7月9日、名古屋地裁は、1994年9月から10月にかけて起こった「連続リンチ殺人事件」の3被告に判決を言い渡した。主犯格の19歳の少年が死刑、18歳の2少年が無期懲役の判決だ。しかし無期懲役は、事実上10年以上の有期懲役でほとんど社会に復帰できるという。
今回の判決に対して、弁護士や極刑反対の人権派は、「短絡的、場当たり的な少年犯罪特有の心理状態での犯行であり、矯正の可能性も十分にある」とコメントしている。しかし今回の事件は、10日間もの永い間の度重なる犯行であり、短絡的・場当たり的犯行と言いがたいのではないか。また罪の意識がなく、確信的で、性格的に大きな問題のある犯行であったように思われる。
昨年4月に私のHP「PSコラム」で「効果的な牽制球が必要だ!!」と題して、以下のように記述している。
≪いかなる理由があろうとも、他人の金品を奪ったり、傷害を加えたり、かけがえのない生命を奪ったりすることは許されないことだ。人間が生きていく上での、この基本的なルールを忘れてしまっての論議が多い。
少年であろうと成人であろうと、自分の犯した罪に対して責任をとるのは当然のことだ。極端にいえば、少年より下の子供や幼児についても同様の自覚を持たせることも必要だ。自覚が持てない年少者にとっては、「他人の物を奪うと尻をたたかれて痛い思いをする」とか、「ミルクが飲めなくなって腹が空く」とか、本能的に肌で感じとれることができるような牽制的な罰が必要だということだ。基本ルールの自覚がない人間にとっては、厳罰・必罰で強制的に罰せられるということを牽制し続けるしかない。
少年事件に関しても、罰せられなければならないのは加害者の筈であるが、加害者の権利が必要以上に重視されているのではないか。「未熟で矯正の余地がある」等の理由によって減刑されたり、プライバシーが保護されたりである。
自分の都合で関係のない人を殺害した人間に、将来更正して生きていく権利があるのか。何もできずに将来を絶たれてしまった被害者の権利はどうなってしまうのか。被害者はやられ損か。全く不条理な話である。
罪を犯すということに対して、自分自身が拘束され相当な責任をとらなければならないことを強く自覚させ、それが無意識に感じられるような強い牽制機能が必要だ。今はあまりにも加害者の権利のみが尊重され、犯罪に対する牽制機能が少ないように思えてならない。ただし、加害者の明らかな過失によるものや禁治産者の場合は別である。≫
感情的に書いているのではない。人間が共に生きていく上での基本的なルールが崩れかけてきていることに不安を感じているのだ。
|